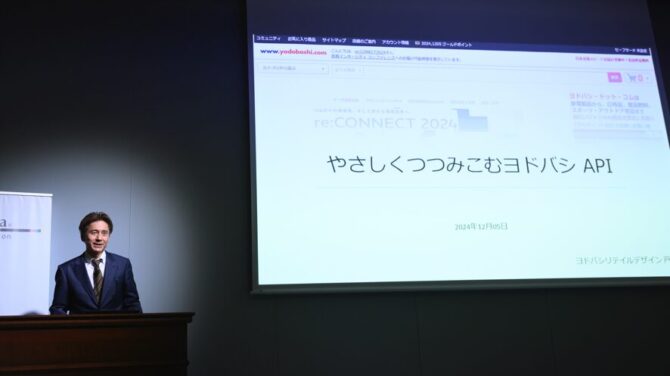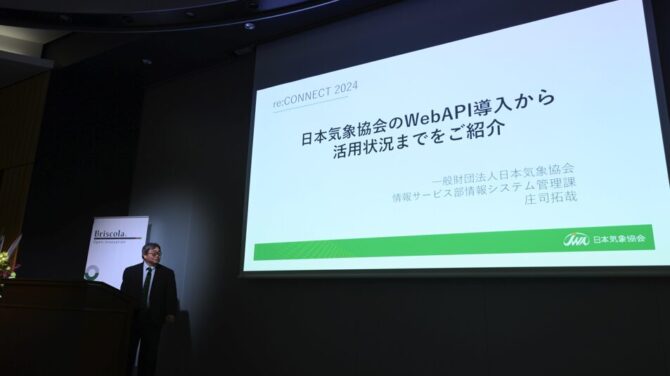re:CONNECT 2024 <Panel Discussion> 企業価値を相乗する「データの民主化」が拓く未来

※本記事は、ブリスコラ主催「re:CONNECT 2024 ~つながりの再発見、そして新たな事業変革へ。」(2024年12月5日開催)でのパネルディスカッションをまとめたものです。
※ パネルディスカッションの動画視聴をご希望の方は、視聴用のリンクをお送りしますのでこちらのフォームよりご連絡願います。お問合せ内容の箇所に「パネルディスカッション動画 視聴希望」と記載の上、ご連絡をお願いいたします。
企業価値を相乗する「データの民主化」が拓く未来
日本経済が低迷から脱しきれない中、常に最先端のデジタルアーキテクチャを活用し新しいビジネスモデルをリードする企業では、データがつながり合うビジネスについてどのように捉え、取り組んでいるのでしょうか。ヨドバシカメラ、ユーラスエナジーホールディングス、日本気象協会の皆さまに議論を交わしていただきました。

<パネリスト>
株式会社ヨドバシカメラ 代表取締役 社長 藤沢 和則 氏 (中央左)
株式会社ユーラスエナジーホールディングス 取締役 常務執行役員 山田 強 氏 (中央右)
一般財団法人日本気象協会 事業戦略開発部 事業戦略開発課 課長 齋藤 佳奈子 氏 (右)
<ファシリテータ>
株式会社ブリスコラ 代表取締役 末貞 慶太郎 (左)
各社におけるデータ活用の動向
末貞)生産年齢人口が減る中で、協力し合って社会の価値を創造していなかければなりません。その一助となるのがデータであり、経済効果を生むものと期待されています。皆さんの会社では、データをどのように活用されているのでしょうか。
藤沢氏) ヨドバシカメラは小売業であり、物を仕入れて、お客様にご案内して、販売するのがサービスの本流です。インターネットにも早くから対応するなど積極的にIT投資を続けてきましたが、特に最近はAIが実用的になった時代に対応するために、今までのサービスをAPIで外部から利用できるようにすることが大きなテーマとなっています。
山田氏) ユーラスエナジーホールディングスは風力発電の老舗企業で、国内最大の発電容量を誇ります。再生可能エネルギーの固定価格買取制度が終了に向かい、市場に連動した価格で電力を販売するようになるという大きな変化点にあります。これまでのデータ活用は、設備の異常が発生する前に停止するといった用途に限られていました。今後は価格を予測して高いときに売れるようにすることはもちろん、発電量の計画値と実績がずれると課せられるペナルティを最小化するためにデータの活用が必要です。
末貞)そのためには天候情報が欠かせないと思いますが、気象協会ではどのような取り組みをなさっていますか。
齋藤氏) 日本気象協会は70年以上の歴史がある企業で、自治体や国、企業向けにスペシャライズした気象データを作りご提供しています。新たなご依頼へ対応しようとすると、データのファイルフォーマットが多種多様であり、また仕様書もさまざまであるため、容易に提供しにくい状態が長く続いていました。それをブリスコラの協力を得てAPI化することによって、気象データを皆さまに活用していただきやすい環境が整ってきました。
APIによるデータのオープン化がもたらす価値共創の姿
末貞)データが連携することによる価値創造に、APIは欠かせないと考えます。APIによって皆さまのビジネスや社会がどう変わるとお考えですか。
藤沢氏) 生成AIがお客様との接点を大きく変えると思いますが、生成AIは最新の情報を知らないところが弱点です。例えば、冷蔵庫の機能については素晴らしい説明をしてくれますが、「今日届けてくれて、いちばん安い販売店は?」と聞いても答えられません。
これを克服するのがデータの民主化です。ヨドバシカメラでは2040年まで通用するアーキテクチャを目指しており、その中でAPIを通じたデータの民主化を実現したいと考えています。
冷蔵庫の例であれば、販売価格や在庫、配送リソースといった情報を、APIを介して生成AIが利用できるようにした上で、最終的にヨドバシカメラで注文していただけるようにしたいのです。 また、APIで情報を提供するだけでなく、当社が持つ配送や倉庫、決済、ポイントサービスといったリソースのさまざまな活用を構想中です。接客もリソースの1つで、例えばレコードプレーヤーの専門知識を持つ社員を予約できるような、接客予約のAPIを作ろうとしているところです。いずれ接客がUber化し、「ヨドバシの社員よりも詳しいぞ」という方が、インターネットを通じて社員に代わって有料で案内するようなサービスも作っていけるはずです。
山田氏) エネルギーマネジメントシステム(EMS)には核となるデータベースがあり、これをAIに利用することで発電量の予測を精緻にしたいと考えています。ここは競争領域であるものの、当社は老舗であり発電量では国内最大勢力を持っていますので、予測の元となるデータが多く有利です。一方で、競合となる同業他社とも手をつなげば、より多くのデータをもとにさらに精緻な予測値を出せるようになり、ひいては世の中のためになるとも思っています。APIによって競争領域を共創領域にすることが可能なのです。
外部のプロによるデータや処理結果を取り込み、一方で、私達が持っているデータも活用していただくことが、後れを取らないためにも必要です。もう自前主義にこだわる必要はない時代だと思います。
こうした理想的な概念を具現化する取り組みは、すでに進んでいます。当社グループでは、再生可能エネルギーの需給双方の事業者が利用可能なVPP※プラットフォーム「ReEra」を提供しており、最適制御により、発電計画と実績の差の最小化および市場収益の最大化が可能です。また、需要家の電気料金削減に貢献する機能も有しています。
※VPP(Virtual Power Plant)とは、自然エネルギー発電所をはじめとする分散電源や蓄電池・EV・ヒートポンプなどをIoTで管理することにより、1つの発電所のように制御して系統に調整力を提供するソリューションです。
出所:https://www.terras-energy.com/ja/business/reera/
齋藤氏) 当協会は長らく「命を守るために気象予測を外してはいけない」あるいは「温度が1度変わると大きな損失が出てしまうので予測を外してはならない」といった社会インフラを司る企業のお客様が中心でした。それがこの10年ほど、サプライチェーンや物流系の企業で気象データを活用したいという要望が増えてきています。また、1時間後や1分後の予測値ではなく、需要予測に必要な長期のデータを求められることが多くなりました。例えばアパレルの場合、気温に合わせてバーゲン時期を調整することで、無駄なく利益を確保することができます。
また従来、気象データを利用するのは大手企業が中心でしたが、気象データをAPI化してからは、スタートアップ企業の方が小さく実証を始めやすくなりました。例えばスキー関連のベンチャー企業の場合は、湿度のデータから雪質を予測して顧客へ提供しているところもあります。
末貞)皆さんのお話を伺うと、データをオープンにして連携し合うことで、新しい価値を作れるという点が共通していますね。
開かれたデータが、地域と企業の魅力を引き出す
末貞)ブリスコラではスマートシティに関わっており、会津若松市では市民も地域も企業もつながることでそれぞれが幸せになる「三方よし」を目指しています。これからの日本では地域との連動が欠かせないと思うのですが、データが開かれることを踏まえた地方創生についての考えをお聞かせください。
藤沢氏) 日本中の好きな場所に住んで、好きなサービスを受けられて便利に暮らせる社会を実現するには、「今日は時間に余裕があるから働けます」、「空き家があるので貸せます」といった情報を発信し、APIを通じて必要としている人が探しあてられる仕組みがあればいいですね。最近、実は勝浦市が涼しくて夏に過ごしやすいというニュースがありましたが、そういう知られていなかった情報をAPIでみんなが発見していけるようにできれば、地域も面白くなるかなと思います。
山田氏) 再エネの発電所はほぼ過疎地にあるため地方創生と密接な関係にあり、私どもは昨年、地域創生推進部という地方創生の専任チームを作りました。
過疎地で電力を作るのにはいくつか課題があります。大変な投資をして送電網を構築しなければ都市部まで運べませんし、送電ロスもあります。また、メンテナンスのために人員を置く必要があります。当社は北海道の稚内に発電所を持っていますが、国による本州までの送電網の建設には時間がかかるため、現状ではこれ以上発電量を増やせません。
一方で、カーボンニュートラルは待ったなしです。そこで工場を建設するなどして需要自体を稚内に持っていき、電力の地産地消と雇用創出を同時に実現するのが美しい形ですが、地元の人口が少なく寒く厳しい土地でもあるので、かなり難易度が高いのが現実です。しかし、例えばデータセンターの誘致であれば少ない人数でも運営でき、少なくとも固定資産税で貢献できるはずです。
都市部に人口が集中している理由の1つとして、電力を効率的に供給できるから人が集まってきたのではないかと考えられ、その逆で電力を分散することで社会を変えることも可能ではないでしょうか。
齋藤氏) 数年前にスタートアップ企業の方から、瀬戸内海で物流船の漁労長が高齢化のため引退し、物流網を維持することに課題が出ていることを聞きました。陸だけではなく、海域の細かなメッシュ予測を提供できれば、自動運行の仕組みに活用いただけます。情報をAPI化するなど使いやすい形に再加工して提供することが、地域の課題解決につながると考えています。
末貞)データを公開して、リアルタイムな情報がすぐに見られるようにすることがポイントかもしれませんね。
新しい価値創造モデルのきっかけをいろいろ教えていただい、てありがとうございました。